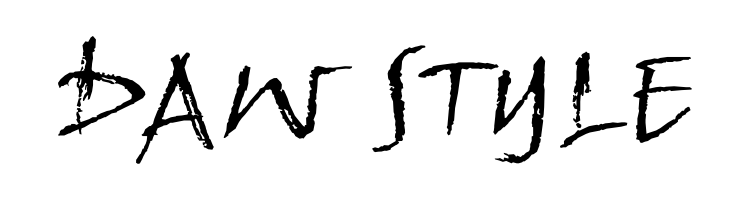普段みなさんが聴いている市販されているCDであったり、Apple Music、Spotify、YouTube Music、Amazon Musicなどでストリーミング配信されているサブスク音楽は、大きく分けると楽曲制作(作詞/作曲/編曲)・レコーディング・ミックスダウン・マスタリングという順序の5つの制作過程を経ています。
作詞や作編曲だけでなく、DTM・DAWソフトを使用してミックスダウンやマスタリングを自分自身で行っている人は、すでに経験済みだと思いますが、ミックスダウンやマスタリングのときのコンプレッサーやイコライザーなどのエフェクターはコツをつかむまでは本当に大変な作業です。
しかし、コンプレッサーやイコライザーなどのエフェクターのコツをつかむことができなければ、作品のレベルアップをすることは難しいです。
最近では各パートのオーディオファイルを解析して自動的にコンプレッサーやイコライザー処理をしてくれる便利なAIプラグインも多数あり参考になりますが、やはり各エフェクターの知識を持っていないとサウンドクオリティーの上級者になることは難しいです。
STEP1:楽曲制作(作詞・作曲・編曲)
作曲・編曲が先

人により楽曲制作の手法やプロセスは違いますが、ポピュラーミュージックの世界では作曲・編曲(アレンジ)が先で、仮歌やシンセのメロディーの上に歌詞を付けて行くという手法が圧倒的に多いです。
現在だと作編曲(作曲・編曲)はDTM・DAWソフトを使用するというのが当たり前になっていますが、作曲に関しては簡単な録音機器(昔で言うラジカセなど)をメインにしている人も多いです。
現在はスマフォのボイスメモなどを利用すると思いますが、ラジカセなどにメロディーを残すのは昔からあるスタンダードな作曲法です。
思い浮かんだメロディーを即座にスケッチ感覚で残しておくというのは、時代が変わっても最強の作曲法なのかもしれません。
プロで活動する場合の作曲・編曲レベル
メジャーでの活動の場合はコンペに勝たなくてはいけませんので当然ですが、それ以外の作曲の仕事でも、作曲と編曲の両方の高いレベルがプロで活動する場合は確実に必要となります。
デモ音源を作っても、自動伴奏ソフトを使ったチープな編曲や、弾き語りの音源では、音楽制作ツールを誰でも手軽に揃えることができる現在では声は掛からないと考えて間違いないです。
STEP2:レコーディング
自宅でも高音質でレコーディングが可能

自宅でのレコーディングだと歌の録音とギターの録音がメインになります。DAWシステムの普及により自宅でも高音質でレコーディングすることが可能です。
レコーディングというと難しいイメージがあると思いますが、パソコンメインの自宅スタジオの場合は簡単に言えばオーディオデータをDAWソフトへ取り込む作業です。
自宅スタジオでのレコーディングで、DAWソフト以外に揃えておきたいのは「スタジオマイク」と「オーディオインターフェイス」です。
この辺りは「初心者のための宅録スタジオ・ガイド」が参考になると思います。

クオリティーの高いボーカル録音
やはりレコーディングで最も気を使うのは、楽曲の顔であるボーカルトラックですが、低価格な高音質マイクも増えたために、現在は誰でも手軽にクオリティーの高いボーカル録音を自宅ですることが可能になりました。
STEP3:ミックスダウン
2MIXにまとめ上げる作業

ミックスダウンはレコーディングした各パート(トラック)の様々なサウンドの音量や定位をバランスよくミキシングして、ステレオ・2トラック(2MIX)にまとめ上げる作業です。
エフェクターの設定など多くの方が頭を悩ませる作品のクオリティーを大きく左右する作業ではありますが、しっかりと編曲やレコーディングができていないと、いくら時間を掛けても上手くは行きません。
またプラグイン・エフェクトを多数使用するので、ストレスのないミックスダウン作業のためには、ある程度のスペックの高いパソコンも重要になってきます。
プロで活動する場合のミックスのレベル
このサイトで紹介している「世界の超一流ミックス/ミキシングエンジニアたち」や、メジャーで活動するミキシングエンジニアほどの知識やスキルは必要ありませんが、低価格で制作環境を手に入れることのできる現在では、高いレベルでのミックスダウンのレベルが必要です。
音楽制作会社で作曲家を募集している場合も、基本的には編曲だけでなくミックスダウン込みというのが暗黙了解となっています。

STEP4:マスタリング
最終行程マスタリング

ミックスダウンが終わると最終行程のマスタリングです。マスタリングには大まかに分けると、音圧レベルや質感の補正などの音を作り込んでいく作業と1枚のCDとして聴いたときに不自然にならないように各曲の音量などのバランスを取って行き調整する作業があります。
最終行程ということもあり、マスタリング作業で市販されている楽曲と自分の曲とのクオリティーの違いに気付く人も多いです。
この作業ではマスタリング・エフェクターであったり、ミックスの良し悪しが重要になると同時に、効率のよい作業の決め手となります。
DAWスタイルで「マスタリングある意味では究極ガイド」の連載を開始しましたので、マスタリングの技術をアップしたい人などは参照してみて下さい。
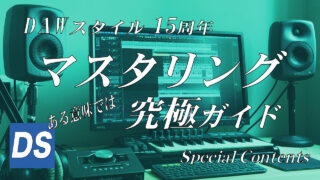
プロで活動する場合のマスタリングのレベル
ミックスダウンと同様に、メジャーで活動するマスタリング・エンジニアほどの知識やスキルは必要ありませんが、高いレベルでのマスタリングのレベルは必要です。
Apple Music、Spotify、YouTube Music、Amazon Musicなどでサブスク配信するときには審査がありますが、けして厳しいものではありません。
そのためサブスク配信の審査に通すことができる最低限のマスタリングのレベルは身につけておかなくてはいけません。