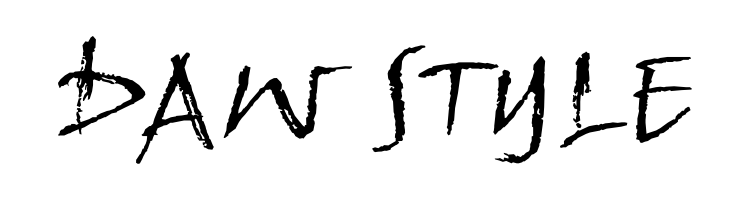あくまでも一般論ですが、プロを目指していてプロでやって行く可能性があると思われる方には、遅くても大体25歳くらいまでには、仕事の規模の大小などは別としても、レコード会社だったり音楽プロダクションから何らかの話が一度はあります。
その後にボーカルやバンドなら、本格的なデモ音源をスタジオで制作したり、ライブを見に来てもらったりという形になり、クリエーターならもう何曲か聴いた後に、楽曲コンペに参加させてもらうという運びになると思います。
近年だと、YouTubeなどで爆発的な人気のある人には声が掛かる場合もありますが、すでにYouTubeなどは、レッドーオーシャンの飽和状態です。
また確率的にはゼロではありませんが、SNSでの発信や宣伝など、音楽以外のところで、かなりの労力を割かなければなりません。
そのなこともあり、プロ志望の人の一番の近道は、やはり音源のクオリティーを仕事レベルまで上げてゆくことです。
自分の音源をチェックする
聴いてもらう以前の問題

何度もデモを送り続けたり同じ音源を数十社に送ってみても、そのような話が一度もないだけでなく、応答すらないという人もかなりの数でいるとは思いますが、一度自分のデモ音源をチェックした後に以下の項目を厳しい目でチェックしてみて下さい。
デモ音源を聴く人もみなさんと同じ人間なので、以下の項目に一つでもあてはまっている方はデモ音源を送っていても、まともに聴いてもらう以前の問題で弾かれている可能性が大きいです。
YouTubeなどで作品を公開している人は30秒も聴かれないで、再生をストップされてしまっている可能性があります。
公開作品やデモ音源のチェック項目
- ボーカル志望なのに声がオケに埋もれていたり何を歌っているかわからない。
- 現在の音楽シーンを持論を並べて否定している割にはレベルがない。(他人に厳しいが自分にはやたら甘い)
- 鼻歌をアカペラと呼ぶ。(歌とユニゾンで笛の音が入っているのも同じ)
- エアレベルでの録音で雑音だらけで音が悪すぎる。
- 誰かのモノマネカラオケ自慢。
- カラオケボックスなどでのプラグマイクを立てての録音。(最後まで聴くのはまず無理です。)
- 一昔前のデモ音源のクオリティーレベル(クリエーター志望なら、しっかりとマスタリングまでしましょう。)
- あきらかにダメモトで出して来ている音源。
- わたしの才能を理解して的なクオリティーの低い音源。
- ライブ音源。(イントロが長かったり、内輪受けで音はかなりヒドイ)
- 声がキンキンしていて耳が痛い。(送って来た人の耳を疑います。)
- 募集プロジェクトを理解していない。
音源が弾かれている可能性
上記した「公開作品やデモ音源のチェック項目」に一つでもあてはまっている人は、ある例外を除いては残念ながらスタートラインに立つ以前の問題で弾かれている可能性が大きいです。
その対処方法と詳細は次のページ以降で説明しています。今までデモ音源を音楽事務所やレコード会社に送ってはみたものの、全く相手側の反応がなかった人は参考にしてみて下さい。
音質が問題にならない場合
ボーカルの実力がわかる音源
前記した「こんな音源は評価される前に弾かれる」を読んで「音質はまったく気にしないと応募要項に書いてあるところもあるのですが?」という質問がありそうなので書いておくと、確かにそういう場合もあります。
例えばボーカルの場合はチェック項目に当てはまっていない限りは、リズム感であったり音程や声質を知りたいので、しっかりとボーカルの実力がわかる音源であれば、もちろん限度はありますが音質は問題ないと思います。
最近だと「歌ってみた」などもあり、自宅でレコーディングできる環境を整えているボーカル志望の人も増え、ボーカルレベルは非常に上がっていますので、「歌が好きという気持だけは誰にも負けません!」というような感じだと、さすがに難しいです。
将来性を期待して
また数年後を見越した将来性を期待している10代の人などは例外にあたり、音質は確かに気にしません。しかし可能性を感じることができるかどうかというのが非常に重要です。
例外という点でもう一つ書いておくと、男女ともにルックスが良くビジュアルが優れている人も例外にあたります。形だけの募集でない限りは、ルックスがよくて歌が上手ければ、音楽事務所やレコード会社が声を掛けないはずはないです。
デモ音源は名刺みたいなもの
デモ音源の説得力
DTM・DAWの発展により自宅録音が整った現在では誰でもそこそこな作品ができてしまいます。
そのような現状において、ボーカルにしてもバンドにしても鼻歌やラインを使わずにエアレベルで録音した引き語りの曲やカラオケBOXなどで作ったデモを「これがわたしです。よろしくお願いします。」と手渡したとしても、正直なところほとんど説得力はありません。
ましてや自分の曲が聴かれる前の人の音源が、しっかりとミックスダウンやマスタリングまでされている作品だったら、貧相なイメージを聴き手に与えてしまっても仕方のないことです。
スタートラインに立つ近道

機材的にもプロもアマチュアも大差のなくなった現在においては「こんなに努力しているのだから、いつかは自分の才能を認めてくれる時代が来る」というスタンスで片手間だったり、ダメモトで音楽活動をしていても、もちろん、それで認められるという人も、なかにはいますが、年だけ取ってしまいます。
そのため例外の人を除く方は、やはりデモ音源をレベルアップさせることが、確率的にもスタートラインに立つ一番の近道となります。
「プロでの活動」を念頭にするのであれば、自分の作品にも他人の作品を評価するときと同じように、厳しい目を持つことが重要です。
デモ音源の第一印象とクオリティーは重要
デモ音源を制作して自分の才能や可能性を理解してもらおうと誰かに聴いてもらうということは、会社の面接だったり、仕事上で交渉先の人にはじめて会うというのと同じだと考えると分かりやすいと思います。
音質にシビアになってきている
面接などでは相手に与える第一印象が重要になってきますが、デモ音源もまったく同じで第一印象は重要です。
このページで記載している「こんな音源は評価される前に弾かれる」にあてはまっている方は、はじめて会う人にダラシナイ格好で会いに行くのと同じです。
そのため公開作品やデモ音源を聴く側も音質に関してはかなりシビアになってきているので音楽人としての第一印象は悪いです。
鼻歌やカラオケBOXなどで、マイクを立てたエアレベルで録音した音質では、自分では良いと思っていたとしても、顔も知らない第三者が聴けば正直なところウンザリしてしまいます。
欲しいのは即戦力
自宅でもクオリティーの高い音楽制作をすることができる現在において、募集する側が「将来性を期待して募集しているのか?」「即戦力を期待しての募集なのか?」によっても違いはありますが、作曲、編曲をするサウンドクリエーターの場合は、将来性を期待しての募集というのは極めて少ないと考えておきましょう。
それはサウンドクリエーターの場合は大小問わず音楽関連企業の欲しい人材は、作曲、編曲だけではなく、ミックス、マスタリングまでを行うことのできる即戦力だからです。
近年では、YouTube Music、Apple Music、Spotify、Amazon Musicなどでストリーミング配信のみのリリースの場合はミックスやマスタリングの専門エンジニアを介さない場合もあります。
そのため一昔前なら声が掛かっていたかもしれないデモ音源のクオリティーでも、現在だと声は掛からないと思って間違いないと思います。