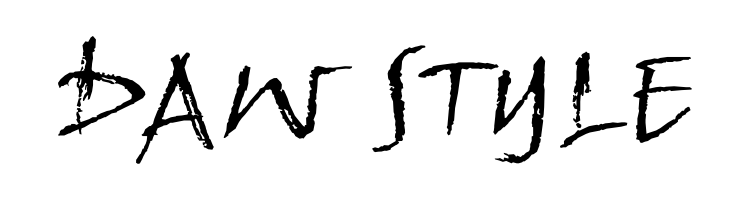第2回目の『マスタリングある意味では究極ガイド』ではマスタリングの作業と現在のマスタリング事情について書いてゆきます。
マスタリング作業は「各曲の音量などのバランスを取る作業」と「音圧レベルや質感の補正する作業」の2つの作業に大まかにわけることができます。
2024年に限定公開した記事ですが、2006年にスタートした『音楽制作必勝講座』を2025年07月で閉鎖することにしましたので、DTM・DAWのマスタリングの基礎講座1「マスタリングとは 〜曲の音圧と迫力〜」で記載していたことも追加して再編集して公開しています。
マスタリングの作業
市販されている曲は迫力の違いとマスタリングとは?

ストリーミングで音楽を聴くことが主流の時代となりましたが、CDで音楽を聴く時代が主流だった頃は、市販されている曲と自分の曲を並べて聴き比べたときに、自分の曲の音量が小さかったり迫力がないと感じている人がかなり多かったです。
市販されている曲に迫力があるのはミックスダウンが行われた後に、最終行程であるマスタリングという作業が行われているからです。
このマスタリングには主に「各曲の音量などのバランスを取る作業」と「音圧レベルや質感の補正する作業」の2つの作業があります。
各曲の音量などのバランスを取る作業
最近はYouTube、Apple Music、Spotify、Amazon Musicなど各音楽プラットフォームのほうで勝手に音量調整(ラウドネス調整)がされますが、まず一つ目の「各曲の音量などのバランスを取る作業」は各曲の音量などのバランスを取って行き調整する作業です。
複数の楽曲を収録するアルバムの場合は楽曲ごとにミックスした人が違った場合は音量差や質感の違いがどうしても出てきます。
そのため複数の楽曲を1枚のCDとして聴いたときに不自然にならないように、各曲の音量のバランスを取り調整してゆきます。
アルバムのなかには曲調も違う場合もありますので、マスタリング時に補正してあげないと、どうしても不自然になってしまいます。
音が小さければリスナーがプレイヤーで音量を上げればよいというような乱暴で自分勝手な考えを持っている人もいますが、リスナーにしてみれば楽曲ごとにボリュームの調整をしたりすることは面倒です。
アマチュアの世界では通用しても、1枚のアルバムのなかでリスナーに楽曲ごとにボリューム調整させるというのは商品として音楽をリリースしているプロの世界ではあるはずがありません。
音圧レベルや質感の補正する作業
次にマスタリングで「音圧レベルや質感の補正する作業」は、ミックスダウンが終了した2ミックスの音源にEQ、コンプ、リミッター、マキシマイザーなどのエフェクターを駆使して音圧レベルやサウンドの質感の補正などの音を作り込んでいく作業です。
現代のマスタリングではこの「音圧レベルや質感の補正する作業」が最も重要な作業となりますが、ストリーミング時代となり各音楽プラットフォームで音量調整がされるようになってからは、音圧レベルの大きさに関してはそこまでシビアにこだわってサウンドを追い詰める必要はなくなりました。
補足として記載しておきますが、CD主流の時代はこの作業の後にCDに書き込まれたり、MP3ファイル等へ変換されますので「音圧レベルや質感補正」は正確にはプリマスタリングです。
しかし暗黙の了解的に、マスタリングエンジニアが行う2ミックスのEQ調整や最終レベルを決定する作業のことをマスタリング作業と多くの人が呼んでいます。
そのためプリマスタリングをマスタリングと呼んでも、それで話は通りますので、まったく問題はありません。
DAWソフトで誰でも簡単にマスタリング作業を行うことができるようになった時代に「それってプリマスタリングだよね?」というような感じで「音圧レベルや質感補正」の話をしているときに、水を差す人に違和感を覚える人のほうが圧倒的に多いはずです。
現在のマスタリング事情
目安がRMSからLUFS重視の時代へ

詳しくは実践ガイドのほうで書いてゆきますので、ここでは細かく書きませんが、現在のマスタリングの音量の単位の基準は「LUFS(Loudness Units relative to Full Scale)」です。
CD時代は音の平均的な強さを示す「RMS(Root Mean Square)」がマスタリング作業時の目安となっていましたが、ストリーミング時代では聴感を基準にしたオーディオのラウドネスの単位「LUFS」が目安となっています。
作曲家にマスタリングは必須作業
DTMやDAWが低価格になり誰でも費用をかけることなく手軽に音楽制作を始めることができる時代になったために、作曲家でも現在はミックスダウンからマスタリングまでできるのが当然です。
一昔前は作曲家はミックスやマスタリングまでの技術はそれほど必要ではありませんでしたが、プロで活動したい人や、配信サイトで多くの人に評価されたい人は、豊富な知識や経験が必要となりますが、マスタリングも必須のスキルとなります。
楽曲コンペなどでも、大昔は弾き語りの音源など音質などは関係ない音源もありましたが、最近は完成形に近い音源が多いです。
ある程度完成形を見せなくては、現在の楽曲コンペで勝つことは難しいため、弾き語りなどでコンペに参加する人は少なくなっています。
レコード会社や音楽事務所が実績のない作曲家にコンペ用にプロのエンジニアを付けてくれるというのは予算の問題もあり難しいというより、まずあるはずのない話です。
現在でも音圧は必要か?
各音楽ストリーミングサービスではオーディオのラウドネスの単位「LUFS」の基準が定められていますので、その音量レベルに達していればよいのじゃないか?と考えがちです。
しかし曲のジャンルにもよりますが、ポピュラーミュージックでは、ある程度ラウドなミックス & マスタリングを心掛けずにストリーミングサービスの-14 LUFS ~ -16 LUFSの基準に合わせてしまうと素人感丸出しのスカスカな音となってしまいます。
ストリーミングでの配信に限定すれば一時期の過剰なまでの音圧競争ほどの音量は必要ないですが、現在でも音圧は非常に重要で必要です。
尚、音圧競争は終わったと言われていますが、マスタリング・プラグインが大きく進化したこともあり、ラウドネス制限のないハイレゾ配信などの「LUFS」は音圧競争時代よりもさらに大きくなっています。
クオリティーがなければ評価される確率は低い
誰でも気軽にアップロードすることのできるYouTubeなどの動画配信サイトでは、音楽だけでなく映像でもプロのクリエイターが参入してきています。
マスタリングまでしっかりとできる音楽ストリーミングサービスに配信リリースしている実力者も、YouTubeではコンテンツIDによる収益化ができるためYouTubeにも配信する人が増えてきています。
特にコロナ以降は参加者が増えレッドオーシャン状態で、配信サイトが普及する前の駆け出しの時代とは違いますので、しっかりとミックス & マスタリングされていないクオリティーのない作品では評価される確率はウケ狙いは別としてかなり低いでしょう。
音楽を舐めるなよ!と思われないように
例をあげると音楽活動と呼べるかどうか微妙なカラオケの延長線上でしかないYouTubeへ動画をアップしても50再生も行かない歌い手と呼ばれている人たちです。
ピッチ補正ソフトも簡易なものならお小遣いで買えるくらいの低価格になり、音痴ですら上手く聴かせることができる時代に、カラオケの延長線の音源などは、ルックスが優れてでもいないと、ほとんどの場合で評価の対象にすらなりません。
XなどのSNSでは暗黙の了解で実際には音源を聴かずに歌い手同士でイイね!を押し合う無意味な習慣があります。
SNSではイイね!が100越えているにも関わらず、YouTubeでは10再生とかの承認欲求だけが強い自分に甘い低レベルな歌い手が溢れています。
真剣に音楽と向き合っている人間からすれば音の完成度さえもわからないのか?レベルの「音楽を舐めるなよ!」と思える音源レベルですので、そう思われないようにマスタリングまでしっかりと覚えましょう。
第2回目の『マスタリングある意味では究極ガイド』では主に「マスタリングの作業」と「現在のマスタリング事情」について書きました。
ストリーミングでの音楽配信が主流になり、マスタリングの音圧の目安が「LUFS」の時代になりましたが、それでもポピュラーミュージックでは素人感丸出しのスカスカな音にしないために音圧は必要です。